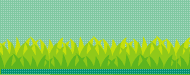|
|
 |
農業共済新聞 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
兵庫県農業共済組合連合会
〒650-0011
神戸市中央区下山手通
4丁目15-3
TEL
078-332-7154
FAX
078-332-7152 |
<会議室の予約先>
TEL
078-332-7165
FAX
078-332-7172 |
| |
|
営農ワンポイント
水稲
平成15年3月4週号の農業共済新聞兵庫版で掲載した水稲の病害虫に関する「ワンポイントアドバイス」をまとめました。 |
■米の品質向上は深耕から
兵庫県立農林水産技術総合センター
専門技術員 三崎 恒敏 |
|
ここ数年、県下の水稲極早生品種(「コシヒカリ」「キヌヒカリ」など)の1等比率が低下しています。乳白・心白・腹白・背白粒などの発生がその原因の1つです。これらは、光合成で作られたもみに送る養分(デンプン)が不足した時に発生します。従って、稲の地上部を健全に保つと同時に、根が占める容積を大きくするように栽培管理することが大切です。
まず、深く耕起(深耕)すること。耕起は雑草の発生を防ぐだけでなく、作土を深くし、空気・わら・刈り株・雑草などを土の中へ入れ、有機物の分解を促進し、そして根の張る容積を大きくします。耕起の時期は乾田か湿田か、田植え時期、その年の天候条件などによりさまざまです。耕起する時には、深く土を起こし、「根優先の稲つくり=米の品質向上」の第1歩としましょう。
次に代かきです。代かきはサッと終わらせるのが良いでしょう。その理由は、田面の均平やわらの埋め込みを狙い、代かきし過ぎると、耕起で入れた空気が減り、土の透水や通気を悪くし、根の伸長を妨げる結果となるからです。
さらに浅水の間断かん水励行、生育に応じた中干し、早期落水の防止など根群を深く広げ、登熟期後半まで根の活力を維持する水管理も重要です。
ただし、適期の田植え、土壌に合った資材投入や肥料の選択、適正な追肥、適期収穫など栽培管理の基本技術励行も重要であることは言うまでもありません。 |
| → 水稲・麦・大豆・果樹等に戻る |
| ↑ ページトップへ |
|
|