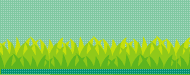|
|
 |
農業共済新聞 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
兵庫県農業共済組合連合会
〒650-0011
神戸市中央区下山手通
4丁目15-3
TEL
078-332-7154
FAX
078-332-7152 |
<会議室の予約先>
TEL
078-332-7165
FAX
078-332-7172 |
| |
|
営農ワンポイント
大豆
平成14年7月4週号の農業共済新聞兵庫版で掲載した水稲の病害虫に関する「ワンポイントアドバイス」をまとめました。 |
■大豆の立ち枯れ性病害防除
兵庫県立農林水産技術総合センター
専門技術員 二井 清友 |
|
| 大豆の立ち枯れ性病害は、連作に伴い土壌中にまん延します。兵庫県内では黒根腐れ病と茎疫病の発生が多く、主要産地では大きな生育阻害要因となっています。今回は、これらの病害対策について解説します。 |
<黒根腐病>
糸状菌による病気で微小菌核によって土壌伝染します。腐敗した根などに生息し、水田化しても長期間生存するため、水田作後でも発病します。根から感染するため主根部は褐変し、細根は腐敗します。病勢の進展は遅く、生育初期から感染しますが急激な枯死は見られず、生育後期の9月中旬以降に株全体の黄化や枯死が多く見られます。
<茎疫病>
卵胞子で土中に長期間生存し、湛水状態になると胞子が発芽・感染します。感染後は短期間で発病し、地際部分から黒褐色に枯れあがり、いずれ枯死します。根は侵されず、葉が青いまま枯れることもあります。病原菌は高温を好むため、発病は7月中旬〜9月中旬に多くなります。
<防除法>
いずれの病害も感染には水分が必要なので、乾燥時の灌水は水をためずに走り水で行い、明きょ、暗きょや高畝などの排水対策をとる必要があります。また、連作を避けることも必要です。茎疫病には大雨直後などにオキサジキシル・銅水和剤を予防散布することも有効です。 |
| → 水稲・麦・大豆・果樹等に戻る |
| ↑ ページトップへ |
|
|