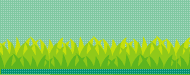■近年発生が気になる水稲の病害虫
ここ数年、稲の害虫では斑点米カメムシ類、病害では内穎褐変病の発生が多くなっています。
しかし、これら以外にも地域により多発して問題となっている病害虫があります。
ここでは発生地域が限られているものの、近年徐々に増加傾向にある病害虫を紹介します。
<スクミリンゴガイ>
南米原産の淡水性巻き貝で、ふ化後約1カ月で成貝(約2.5cm)になり、産卵を始めます。
最大長(8cm)になるまでは約2カ月、総産卵数は約4千個で、5月上旬から用水路の壁や稲の茎に鮮紅色の卵塊を産みつけます。
移植後2〜3週間までの稲を加害し、それ以降は雑草などを食害します。
発生地域の拡大要因は主に水系間の移動によります。
対策としては田植え後の浅水管理、水路からの侵入を防ぐための金網設置、冬期の耕耘などが有効です。
<ニカメイチュウ>
ウンカ類と並ぶ稲の最重要害虫でしたが、発生は次第に減少していました。
ところが平成元年頃から県内の中南部地域で発生数が増加し、その後も発生が恒常化している地域もあります。
稲株や稲わらの中で幼虫の状態で越冬し、6月頃に越冬世代成虫が現れ、その幼虫に加害された稲は芯枯れ茎となります。
さらに、8月頃には次世代成虫が現れ、その幼虫に加害されると白穂や出すくみ穂となります。
対策として、発生した圃場では冬期に圃場(稲株)を耕耘することにより、越冬幼虫密度を低下させることができます。
<白葉枯れ病>
葉縁に沿った細長い波状の白から灰白色の病斑を生じる細菌病で、梅雨時や台風の後などに葉の傷口から病原菌が侵入して発病します。
伝染源であるサヤヌカグサが自生している地域では慢性的に発生しますが、最近は水路の整備などで発生は減少していました。
ところが近年、一部地域では大雨後の冠水などによる発生が認められており、出穂後に発生が急増し、もみに発病するともみ全体が枯死することもあります。
対策としては中生新千本などの罹病性品種を避け、窒素の多施用を控えることが必要です。
<イネシンガレセンチュウ>
このセンチュウは主に種もみ内で越冬します。
播種後、水中に泳ぎだして健全もみ内に入り、その後イネの生長点や幼穂付近に寄生して吸汁加害します。
最初生長点に寄生するため、葉先が枯れてこより状になり油脂状の光沢を生じるので、この症状を一般にホタルイモチと呼んでいます。
このセンチュウが寄生すると玄米の張りが悪くなり、屑米や黒点米が多くなります。黒点米は着色粒として等級格下げの要因となります。
発生田からの種子を用いないのはもちろんですが、発生田からのもみ殻やわらも水田内に持ち込まないようにする必要があります。
|